
和食を食べていますか?ここでは、伝統的な食文化である和食の重要性と保存について詳しく解説します。一汁三菜を基本とする食事のスタイル、うま味を活用した健康的な和食は、長寿や肥満防止にも効果的です。
世界的にも注目されている和食ですが、ライフスタイルの変化などを理由にその伝統が失われつつあります。
和食の良さを知ってもらい、和食離れを避けるためにも和食の歴史や特徴、食文化保存の重要性などについても詳しく説明します。
日本の食文化とは?

日本の食文化といえば和食ですが、そもそも和食とはどのような料理を指すのか理解していますか?
ここでは、和食について詳しく解説し、和食への理解を深めます。
料理のジャンル以上の意味を持つ和食
和食は単なる料理のジャンルではありません。
食材選びから食べ方まで幅広い要素が含まれています。
日本では食事の前に「いただきます」食後は「ごちそうさま」を口にするのが一般的な習慣として根付いています。
それは、料理を作ってくれた人だけでなく、食材を育んでくれた自然、食材そのもの、自然を守ってきた神々や祖先まで、料理に関わった全ての人やものへの感謝を示すための言葉です。
さらに、完成した料理だけでなく料理の手法、構成、器選び、盛り付けまで、日本人の食事に対する気持ちやスタイルが反映されています。
日本が守るべき文化「和食」

和食は、日本が守るべき食文化だと言えます。日本人の信仰やものの考え方が、食とそれを囲む空間に表れているからです。
食文化は、自分たちを取り巻いている自然環境、国や地域独自の文化を背景にして生まれます。
食べ物だけでなく、食事の場、食べ方、おもてなしの心まで、日本人が築き上げてきた食の知恵、工夫、慣習が和食です。
そのため、和食文化を守ることは、日本の伝統文化を守ることにつながると言えるでしょう。
和食の歴史

和食が無形文化遺産として認められていることをご存知ですか。
さまざまな要素を併せ持つ和食がどのようにして誕生したのかなど、和食の歴史について紹介します。
和食の歴史
日本は南北に伸びた列島で、海や川、山、平野といったさまざまな地形があり、地域ごとに気候や風土が異なります。
地域ごとに異なる気候条件により、その土地ならではの四季折々の食材に恵まれています。
そこで、自然の恵みを活かした料理をつくり、大切に食べてきました。
また、食材を無駄なく使うために調理や保存の工夫、器や盛り付け、部屋の飾りまで四季や行事に合わせた特別感をつくりだしてきました。
さらに、海外の食材や料理も工夫して独自のものに変化させ、1つの文化として継承されてきたのです。
和食が無形文化遺産に登録された背景
和食は、四季折々の恵みを大切に、感謝の気持ちと共に受け継がれてきただけでなく、海外の食材や料理も上手に取り入れて、一つの文化として育まれてきました。
このような歴史や過程が、和食の文化として評価されて、無形文化遺産に登録されたのです。
和食のこだわり

和食にはさまざまなこだわりがあります。
ここでは、和食の食材へのこだわりについて詳しく紹介します。
旬を活かす
和食は、旬の食材に合った料理を工夫し、季節感を大切にしてきました。
一年を通じて、食材にはよくとれる時期、美味しい時期があり、これを「旬」と呼んでいます。
現在は食品の流通が発達したことから、旬に関係なく出回っている食品がたくさんあります。
しかし、旬の食材は栄養価が高く味が良いだけでなく、その時期にたくさん出回ることから手頃な価格で購入できます。
旬の素材を積極的に活用することで、素材の持つ旨味や栄養を存分に味わえるのです。
外国から来た野菜を上手に取り入れる
和食でよく使われている野菜ですが、実はほとんどが海外から伝来したものです。
たとえば、ごぼう、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、白菜などは、日本の野菜だと思っている人が多いのですが、ほとんどが海外から伝わったものです。
海外から伝わった野菜は、地域ごとの自然に合うように改良し栽培されたことによって、和食でもよく使われる野菜として定着しました。
和食の特徴
和食の主な特徴について紹介します。
多様な食材の活用と地域特有の食文化
地域ごとに異なる気候や風土から得られる多様で新鮮な食材を使用しています。
また、素材の味わいを活かすための調理技術や調理法を用いています。
優れた栄養バランス
栄養バランスにも優れていることから、和食は健康面でも注目されています。
「うま味」を活用することで動物性脂肪を多用せずに、料理を美味しく仕上げます。
おかげで、長寿や肥満防止に効果的です。
さらに、ご飯、汁物、魚や野菜といった構成は、バランスよく栄養を摂取するのに役立ちます。
四季を表現
料理だけでなく、食事の場で自然の美しさや四季の移ろいを表します。
旬の食材の活用、季節の花や葉、その季節に合った調度品や器を利用することで四季を表現しています。
地域と家庭の絆の強化
食事をする時間を共有することで、家族や地域の絆を深めます。
また、正月などの季節の行事も食との関連性が深いです。
和食が危ない!食文化の保存

伝統的な和食が今、危機を迎えています。
日本人の食生活の変化
1970年代以降、日本人の伝統的な食生活が急速に変化しました。
食の趣向も多様化して、肉類、油脂、乳製品の消費量が増加し、食料自給率が下がったのです。
食糧自給率の低下
日本の食料自給率は下がり続けています。
国内で自給可能な米や野菜、魚などの消費量が減少している一方で、国内では調達が難しい畜産物、加工食品、小麦などの消費が増加していることが大きな原因です。
日本人が食べる米の量は、50年で半減しており、乳製品や肉類の消費量が増えています。
このことから、和食の伝統的なスタイルが変化していることがわかります。
家で調理する機会の減少
家庭で調理するのではなく、出来合いの総菜や弁当など調理せずに自宅で食べられるものの利用が増えています。
その影響で、和食や和食の要素を家庭で使える機会が減少しているのです。
和食の未来

失われつつある日本の伝統文化である和食を継承するためには、どうすればいいのでしょうか?
食材へのこだわり
和食は食材を選ぶことも大切な要素の一つであるため、使用する食材にはこだわりましょう。
幼い頃の習慣が、その後の食習慣をつくると言っても過言ではありません。
そこで、次世代を担う子供たちに、離乳期から食べ物の選び方を教え、幼少期の食の経験を豊富にすることが大切です。
また、食材の鮮度も和食に欠かせない要素の一つです。
流通が発達していても地域で採れた新鮮なものを調理した方が、素材の鮮度や味を損なわない可能性が高いため、できる限り地産地消を心がけましょう。
こだわりの食材を選ぼう
まずは食材にこだわることから心がけてみましょう。
こだわりの食材が購入できる「ミンナノイチバン」を活用してみてください。
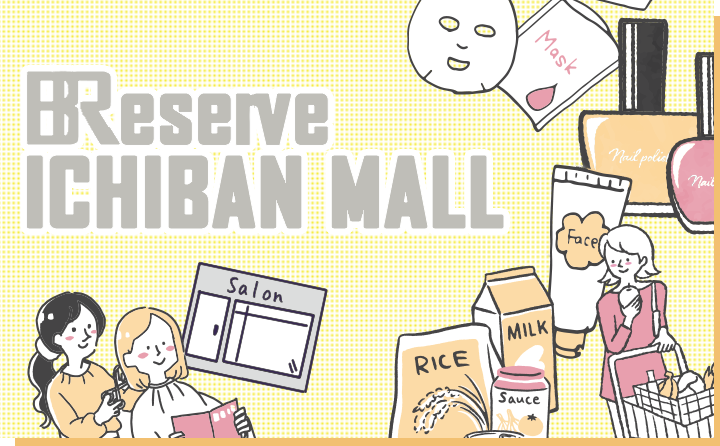
伝統的な日本の文化である和食を守ろう

和食は、食べ物だけでなく食材選びからその食べ方まで幅広い要素が含まれています。
また、海外の食品を上手に取り入れて、自身の文化として定着させてきたことなどから、無形文化遺産に登録されています。
日本の伝統文化である和食が失われつつある現状において、その文化を次世代に継承するために、食材にこだわることから始めてみましょう。











